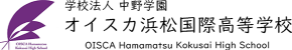SDGsの活動
主なSDGs活動
体験学習

5月 茶摘み実習(1年生)

6月 田植え実習(全校生徒)

10月 稲刈り実習(全校生徒)

植林活動「子供の森」計画
(2年生海外研修)
フィリピンでの海外研修時に植林活動を行う

和地地区環境保全活動(グローバルキャリアコース)
和地地区との協働で、年3回活動
和地地区農村ビオトープ園の管理、梅の木剪定など
部活動

学校横に植林しているマングローブが、
水質にどのような良い影響を与えているのか
天文・自然科学部が継続して水質検査を行っている。

高校生スポーツビーチクリーン実行委員会
スポゴミ甲子園(9~11月)
運動部が中心となって、近隣の高校と一緒に
浜名湖や中田島砂丘のごみ拾いを競技形式で行う

競技形式で堆砂垣設置(女子バレー部)

花いっぱいプロジェクト(インターアクト部)
天浜線の「花のリレープロジェクト」参加
委員会活動

ベルマーク収集(ベルマーク委員会)

「アイシティECOプロジェクト」(ベルマーク委員会)

マングローブ干潟清掃活動(環境委員会)
毎月2回、クラスごとに干潟清掃活動を行っている
環境SDGsプロジェクトチーム

防潮堤に植林した松の手入れ作業

中田島砂丘のゴミ拾い
外来植物の除去作業など

中田島砂丘の砂丘保護活動
堆砂垣を作り、飛砂で砂が減るのを抑えています。

【フードパントリー運動】
松堆肥で育てた「浜名湖野菜」を
NPO法人エヌポケットさん主催の
フードパントリーへ寄付

【屋上菜園プロジェクト】
(グローバルキャリアコース3年「環境デザイン」の授業)
大平台小学校 屋上菜園SDGs総合探究

【フードドライブ運動】
食品ロス削減プロジェクトとして
社会福祉協議会西地区と連携して運動に参加

環境SDGsプロジェクト
インスタグラムもぜひご覧ください♪